- はじめに
- 通貨はもともと情報と信用のネットワーク
- ステーブルコインの登場とリブラの衝撃
- 日本におけるステーブルコインの法整備
- トークン化預金(Tokenized Deposits)の登場
- デジタル通貨フォーラムとDCJPY
- デジタル通貨の本質も情報と信用のネットワーク
- デジタル通貨とこれからの金融インフラ
はじめに

2023年10月12日、筆者が座長を務め、100を超える企業や銀行で構成する「デジタル通貨フォーラム」が構想を進めてきた民間デジタル通貨「DCJPY」の商用化第一号案件が公表された。
DCJPYは、ブロックチェーン・分散台帳技術(DLT)を組み込んだ円建てのデジタル通貨であり、まずは民間銀行による発行が想定されている、その意味で「高度化した民間銀行預金」とも捉えられるDCJPYは、デジタル通貨フォーラムとして、これからの経済を支える上で必要と考える要素を盛り込んだものである。
では、デジタル通貨に求められる要素とは何だろうか。通貨の成り立ちにさかのぼって考えてみよう。
通貨はもともと情報と信用のネットワーク

かつて通貨の発生については、「物々交換の中から徐々に生まれてきた」との見方が通説であった。しかし20世紀以降の人類学・考古学の成果によれば、ヒトが通貨の登場より前に広範に物々交換を行っていた証拠は見つからず、「物々交換起源説」は否定されつつある。むしろ、通貨という強力な情報と信用のネットワークが登場したことによってはじめて、ヒトは広範な交換を行えるようになったとの説が有力になっている。
物々交換を成立させるには「欲望の二重の一致」が必要となる。リンゴを持っている人がこれをブドウと交換したければ、「ブドウを持っていてリンゴと交換したい人」が目の前に現れなければならない。しかし、実際にはそんな偶然はめったに起こらないだろう。
これに対し、人々がその価値への信用を共有する通貨があれば、リンゴを持っている人はこれをまず通貨と交換し、それからブドウを持つ人を探せば良い。この場合、人々はリンゴやブドウの価値を、共有する信用のネットワークを通じて、抽象化され演算の可能な「数値」に置き換え、交換に伴う複雑な情報処理を飛躍的に効率化したわけである。
ステーブルコインの登場とリブラの衝撃
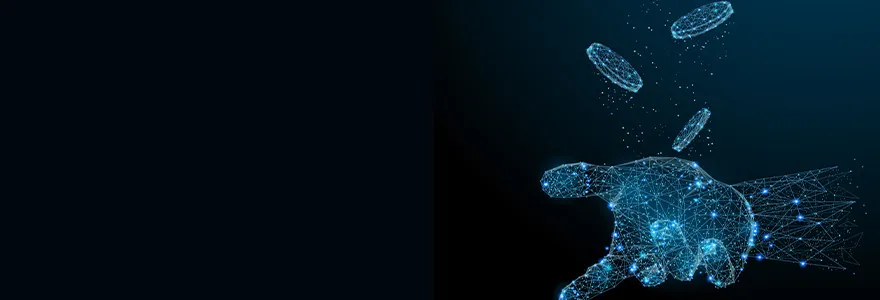
したがってデジタル通貨においても、支払決済手段として使われるには、やはり価値安定と信用が絶対条件となる。この意味では、ビットコインに代表される第一世代の暗号資産が、その価値変動の激しさゆえに支払決済には殆ど使われず、もっぱら投機の対象となったことは当然といえる。誰も、明日価値が下がると思うものを受け取りたくないし、価値が上がると思うものは渡したくないだろう。
一方で、暗号資産の基盤技術であるブロックチェーン・DLTは、中央集権的な帳簿管理を行うことなく、分散型構造のもと、インターネット環境の中で二重譲渡や改ざんの防止を実現でき、「スマートコントラクト」を通じた取引の自動執行機能なども組み込むことができる魅力的な技術である。このため、暗号資産の登場からほどなく、「ブロックチェーン・DLTの果実を取り込みながら、価値も安定した支払決済手段」が求められ、さまざまな「ステーブルコイン」が登場することとなった。
ステーブルコインの種類としては、まず「価値が下がると発行量を自動的に減らす」といったアルゴリズムを暗号資産に組み込むことで価値の安定を図るものがある。しかし、このようなステーブルコインの価値は、実際にはかなり変動する事例が目立つ。
これに対し、預金や短期国債などの裏付け資産を保有することで価値の安定を図るステーブルコインが発行されてきた。このタイプのステーブルコインを世界規模で実現しようとしたのが、フェイスブック(現メタ)が主導する形で2019年に提案された「リブラ」であった。リブラは、複数の先進国の短期国債などを裏付け資産とする「グローバル・ステーブルコイン」を作り出そうとしたものである。しかし、とりわけ通貨の信認が十分でない国々において、リブラが自国通貨の代わりに国内で使われれば、間接的に自国通貨から先進国通貨への資本流出につながる。結局、各国の警戒感に晒されたリブラ計画は頓挫することとなった。
一方で、リブラ計画はステーブルコインへの関心を世界的に高め、多くの国々が中央銀行デジタル通貨(Central Bank Digital Currency, CBDC)の検討を本格化させるきっかけにもなった。
この間、ステーブルコインを巡ってはいくつかの問題も発生した。裏付け資産を持つステーブルコインも、裏付け資産を減らすなどしたり、その質を落とすほど、発行者が発行益を得やすくなるというインセンティブ問題を内包しており、そうなるとステーブルコインの価値も「ステーブル」とは言えなくなる。実際、近年、「価値の安定」を謳っていたいくつかのステーブルコインの価値が大きく下落するケースがみられた。
日本におけるステーブルコインの法整備

この中で、日本では2023年6月、改正された「資金決済に関する法律」(改正資金決済法)が施行された。同法は、ステーブルコインのうち、法定通貨と連動した価格で発行され、十分な裏付け資産を持つものだけを括り出して「電子決済手段」と規定し、法整備を行ったものといえる(上記以外の自称ステーブルコインは「暗号資産」として規制される)。
同法では、電子決済手段の発行者となり得る主体として銀行、信託銀行、資金移動業者、特定信託業者を挙げている。さらに、電子決済手段の「流通」を業として営む仲介者を「電子決済手段等取引業者」(電決業者)と定義している。これにより、ステーブルコインの「発行」と「流通」を別の主体が分業することを可能とした。
ステーブルコインを発行する銀行などからみると、ステーブルコインの発行と流通を分業することで、システム構築負担やAML/CFT対応などを電決業者と分担できる可能性がある。しかし、そのためには十分なインフラ投資とAML/CFT対応ができる電決業者を見つけなければならないし、これらに電決業者がかけるコストは、手数料などの形で発行者も間接的に負担することになる。これらも踏まえれば、発行と流通の分業により直ちにステーブルコインが発行されやすくなるとみるのは早計であろう。
トークン化預金(Tokenized Deposits)の登場

この間、預金にブロックチェーン・DLTなどの新しい技術を応用し、その高度化を図るプロジェクトも現れている。代表的なものとしては、JPモルガン・チェースが主導する”Onyx”、シティバンクなどが取り組む“RLN(Regulated Liability Network)”などが挙げられる。
とりわけ先進国では、預金口座は個人や企業に広く普及している。預金は、銀行規制や預金保険などによりその価値と信用が担保され、現金との一対一での交換も確保されている。この仕組みのもと、個人や企業は多額の支払決済などにも預金を日々利用している。これらに鑑みれば、預金に新しいデジタル技術を活用し、取引を自動執行するプログラムなどを組み込み可能(プログラマブル)にしようという取り組みが出てくることは自然といえる。このような進化型の預金は、最近では“Tokenized Deposits”(トークン化預金)と呼ばれることが多い。
トークン化預金については、既存の制度的枠組みを活用する形で価値安定や信用を確保し、さらにブロックチェーン・DLTなどの新技術を取り込めるメリットが指摘されている。加えて、今後仮に「ホールセール型」(銀行間などの大口決済用)の中央銀行デジタル通貨が発行される場合にも、これとの共存を実現しやすいといった利点も考えられる。
なお、トークン化預金とステーブルコインとの相違は相対的なものといえる。例えば、預金を裏付けとするステーブルコインが発行と流通を分けずに実用に供される場合、経済的効果としてはトークン化預金とほぼ同様と捉えることができる。
デジタル通貨フォーラムとDCJPY

このように、現在の世界の潮流は「価値安定と信用が確保され、さらに新しいデジタル技術も取り込めるデジタル通貨」を目指すものであり、この点はステーブルコインもトークン化預金も同様である。
いくつかの国々で検討が続けられている中央銀行デジタル通貨(CBDC)も、同様の問題意識を共有するものといえる。CBDCはこれまで、バハマ、東カリブ諸国、ジャマイカ、ナイジェリアの4地域で正式に発行されている一方、先進国では検討に時間を要している。預金口座や民間決済サービスが既に普及している先進国においては特に、発行の意義や銀行経由の資金仲介への影響、民間主導のイノベーションへの影響などを慎重に考えなければならないことを踏まえれば、このこと自体は当然とも言えよう。
冒頭に紹介した「デジタル通貨フォーラム」が構想を進めてきたDCJPYは、技術的にはステーブルコインのプラットフォームとしても機能し得る。もっとも、まずは銀行が為替業務としてデジタル通貨を発行し、自ら流通を担うケースを想定している。これにより、DCJPYは銀行預金と同様の価値安定と信用を備えることになる。さらに、多様なビジネスニーズなどを反映したプログラムを書き込める「プログラマビリティ」も実現できる。すなわちDCJPYは、これまで経済社会が築き上げてきた信用の枠組みを活用しつつ、同時にこれからの経済社会を支える情報ネットワークとして十分な機能を備えるよう設計されている。
本年10月に公表された商用化第一号案件は環境価値の取引に関するものであるが、デジタル通貨フォーラムでは、テーマやユースケースごとにさまざまな分科会を設置し、広範な取り組みを進めている。例えば、デジタル通貨を活用した地域経済の活性化や行政事務の効率化、受発注事務の自動化やNFTの取引などが挙げられる。
デジタル通貨の本質も情報と信用のネットワーク

これまでも通貨インフラは、価値の安定と人々の信用を中核としながら、技術進歩とともにイノベーションを遂げてきた。鋳造技術の登場に伴い硬貨が生まれ、紙技術の登場に伴い紙幣が生まれ、電気通信技術の発達を背景に、預金や電信送金、クレジットカードやデビットカードなどが発達した。そして現在、デジタル技術やネットワーク技術の革新が急速に進行している。通貨の本質がもともと情報と信用のネットワークである以上、現在進行中の技術革新は、これまでの歴史上のさまざまな技術革新と同様に、通貨インフラの可能性を大きく拡げる可能性がある。
デジタル通貨とこれからの金融インフラ

民間によるデジタル通貨が、価値安定や信用といった通貨インフラのコア要素を維持しながら、さらに新しいデジタル技術を取り込むことができれば、金融インフラや経済のさらなる発展への貢献が期待できる。さらに民間デジタル通貨には、これまで効率的な資源配分に寄与してきた「市場メカニズムに基づく資金仲介」や「民間主導のイノベーション」を活かせるメリットもある。
現在、経済社会のデジタル化とともに、セキュリティトークン(ST)や非代替性トークン(NFT)、メタバースやWeb3上の価値など、新しいデジタル資産の取引が生まれている。人工知能(AI)を活用した自動化取引や、分散型金融(DeFi)、分散型市場(DEX)などの新しい金融取引も登場している。さらに、非金融サービスの中に金融サービスをソフトウェアとして導入する「組み込み型金融」(embedded finance)も拡大しつつある。民間デジタル通貨は、これらの発展に寄与し、デジタルエコノミー全体の発展に貢献し得る。
また、気候変動対応が全世界的課題となる中、排出権などの環境価値取引が注目を集めている。環境価値は、決められたタイミングで特定の主体により発行される国債や社債、株式などとは異なり、さまざまな主体による環境貢献活動などを通じて、いわば分散的に創り出されるものといえる。したがって、これらを分散型構造のもとで取引できるインフラは、環境価値取引の今後の普及にとって鍵となる。さらに、環境対応自体、従来のリスク・リターンの判断を超える「地球環境へのリスク」の評価といった高度な情報処理を求めるものであり、また、ブロックチェーン・DLTは、クリーンエネルギーのトラッキングや証明にも応用可能な技術である。この中で民間デジタル通貨は、現在の世界が直面している課題の克服にも貢献できる可能性がある。
もちろん、デジタル技術革新を経済社会の発展につなげていくには、通貨インフラの革新にとどまらず、新たに登場している各種デジタル資産への対応や、金融・非金融の連携の促進など課題は多い。デジタル通貨フォーラムとしても、広範な課題克服に向けた積極的な取り組みを続けるとともに、得られた知見を広く社会と共有していきたい。

- 寄稿
-
フューチャー株式会社
取締役グループCSO
山岡 浩巳 氏東大法学部卒、カリフォルニア大バークレー校法律学修士。ニューヨーク州弁護士。IMF日本理事代理、バーゼル銀行監督委委員、日本銀行金融市場局長、同決済機構局長などを経て現職。










