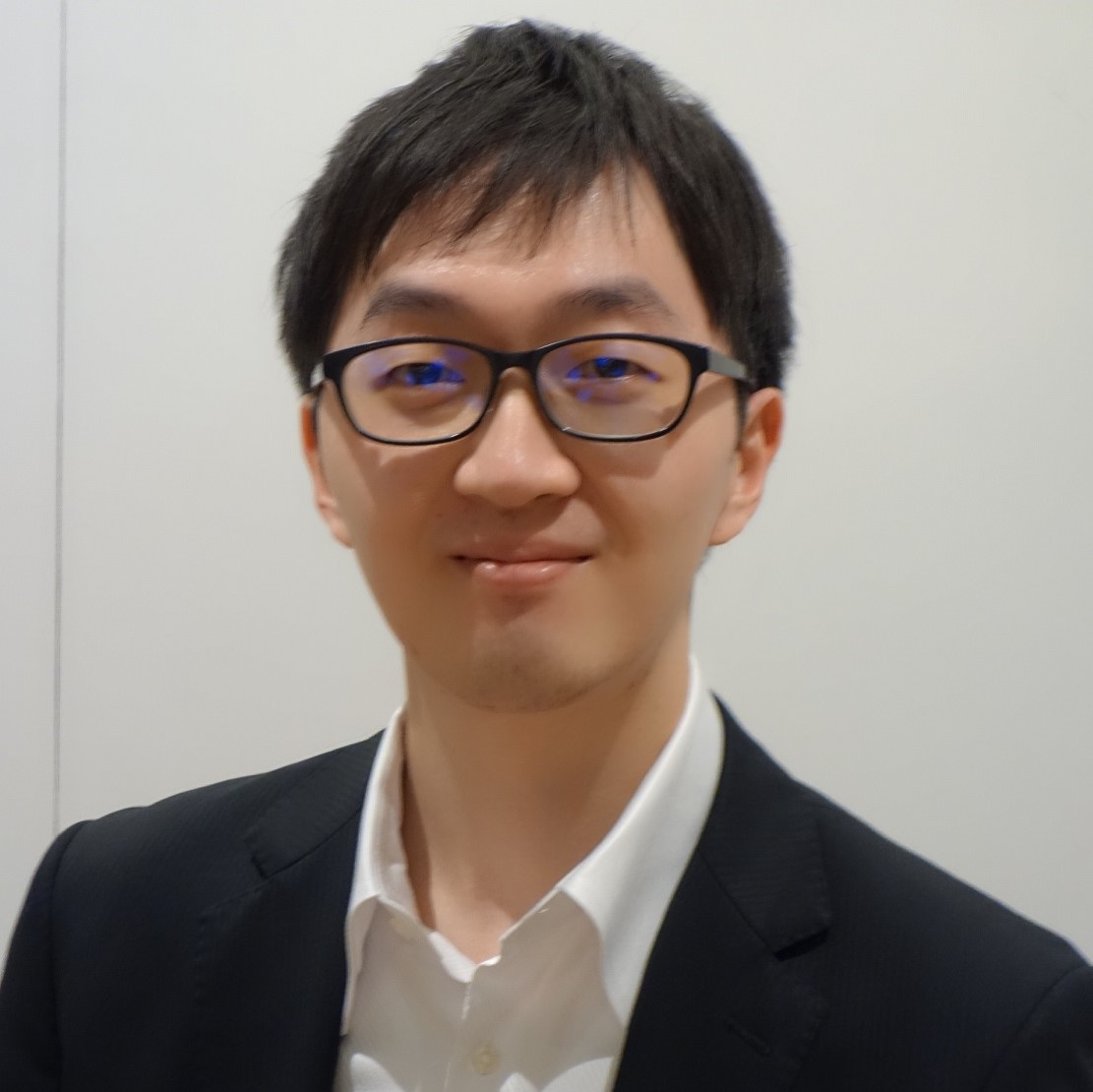- みずほ銀⾏におけるOMOマーケティング戦略
- ジャパンネット銀行様事例にみる環境変化に打ち勝つ顧客接点のつくり方
- 三菱UFJ信託銀行のAIを活用したマーケティングの取組について
- 顧客中心のコミュニケーション実現
~データを活用し、CX(顧客体験)を向上させるには~
みずほ銀⾏におけるOMOマーケティング戦略
- 基調講演➀
【講演者】
-
株式会社みずほ銀行
個人マーケティング推進部 調査役安田 恵 氏
今回は、当行が取り組んでいるOMO戦略の概観について紹介したい。最近OMO(Online Merges with Offline)という言葉をよく耳にするようになった。OMOとは「オンラインがオフラインを融合する」、すなわちオンラインとオフラインが垣根を越えるような形で顧客体験を最大化する、というマーケティング戦略である。
他にオンラインを活用したマーケティング戦略には、OtoO(Online to Offline)、オムニチャネルといったものもある。まずOtoOはWebサイトやEメールといったオンライン上のメディアからオフラインの店舗へ顧客を送客する手法である。オンラインとオフラインは分断されており、一方的な顧客行動を促す点に特徴がある。またオムニチャネルはECなどのオンライン上にある顧客接点と店舗、通販カタログなどのオフライン上の顧客接点をシームレスに統合することで、バリューチェーンの一元管理および顧客利便性の向上を目指すものである。
一方、OMOでは、キャッシュレス決済、IoTプロダクトといった形で全ての顧客接点をオンライン化し、そこにオフラインを含めてしまう。顧客接点をオンライン化する利点は、顧客の購買履歴、商品の利用状況などの行動データが全て取得可能になることである。そして、これらの蓄積したデータを活用し、顧客体験を最大化するべく施策展開を行うこと、これがOMOのベースとなる発想である。たとえば当行の場合、全チャネルにおいて網羅的な顧客データの収集、および配信エンジンの整備を行い、マーケティング活動の基盤を強化している。そして、それを受け、マーケティングセクションでは、収拾したデータを元に顧客のペインポイントや行動データを捉え、企画や施策の計画に反映させる。こうした試みを通して、オンラインとオフラインの垣根を越え、顧客体験の最大化に努めているところである。
さて、ここで実際の施策例を3つほどご紹介したい。
1つ目の事例は、オフライン部分の強化を目的とした利用者参加型社会価値創出施策である。これはオンライン取引と寄付活動を連動させるもので、いわば銀行と利用者が共同で行うCSV活動ともいえるものだ。利用者はオンライン取引の利用を通じて、自分の支援したい団体に寄付を行うことができる。コロナ禍で社会参画意識の高まりを受け、顧客からの支持を順調に伸ばしている取り組みとなっている。
2つ目の事例は住宅ローン関連の施策である。こちらはオンライン部分の強化を目的としたものだ。近年中古物件の需要が都市部を中心に高まった結果、住宅ローンの審査には迅速性が要求されるようになった。そこで当行では、顧客が早く借入手続きを済ませられるようにAI事前診断を導入した。これにより、最短1分で精度の高い事前診断を受けることが可能になった。さらに、このときのデータは正式審査に引き継がれるため、スムーズに正式審査の申し込みができるようになった。また集めた顧客データを使い、各顧客の状態に合ったアフターフォローをも行っている。
3つ目の施策は、貯蓄から投資推進における共創型施策である。当行には「人生100年時代におけるライフデザインのパートナーでありたい」という経営戦略があり、マーケティングにおいても顧客に長期的に寄り添ってサービスを提供することを重視している。これらの理念を実現すべく、資産形成分野における顧客をニーズごとに分類し、それぞれの層に合わせた施策を展開している。
当行ではオンライン・オフラインの規模、利便性を拡大し、顧客体験の最大化を目指している。これからもオンラインの領域を広げる、利便性向上に役立つ新たなサービスをリリースするなど、OMOを推進する施策を続けるとともに、得られたデータ資産をさらに分析して次の施策展開に生かしていきたい。
ジャパンネット銀行様事例にみる
環境変化に打ち勝つ顧客接点のつくり方
-
【講演者】
-
株式会社ジャパンネット銀行 CX統括部 CX企画グループ
髙橋 幸花 氏
-
【講演者】
-
株式会社KDDIエボルバ 法人営業本部 第1営業部
岩﨑 良彦 氏
KDDIエボルバはカスタマーサポートを中心としたアウトソーシング事業を行っており、これまでに金融機関様をはじめとする様々な企業様のカスタマーサポートを支援してきた。今回は弊社が提供しているビジュアルIVRの導入・活用支援などの顧客接点構築のための「デジタルと人的オペレーション」について、実際の事例を交えながら紹介したい。
コロナ禍が本格化して以降、カスタマーサポートの現場でも大きな変化が起きている。特に緊急事態宣言が発令された2020年4月以降は自社の問い合わせ窓口を縮小して営業する企業が増えた結果、電話による問い合わせの利便性が大きく低下した。当社が消費者を対象に実施した企業への問い合わせに関するアンケートによれば、電話による問い合わせ時に関しては「つながるまでにかかった時間が5分以上」だったとする回答が5割超。また、諦めてかけ直したなど、その場で問い合わせが完了しなかったという回答も3割を超えている。その結果、問い合わせ対応の顧客満足度が以前の調査結果より15ポイント低下し、逆に不満足の割合は7ポイントも上昇している。その多くは「電話のつながりにくさ」を理由にしたもので、電話というリアルタイム対応のチャネル特有の課題が浮き彫りになる結果となった。
このように電話やチャットといったリアルタイムのチャネルには、対応が遅れると顧客の不満要因につながりやすいという特徴がある。さらに、コロナ禍以降、約5割の方が電話以外の問い合わせを希望しており、自己解決のニーズも3割近いという現状もある。
こうした課題を解決し、CXを向上させるためには、自己解決チャネルを含むチャネルの拡充やデジタル化、さらに顧客意識・問い合わせ行動の変化に合わせた動線設計が重要だ。
ここで、実際の取り組みにおける成功事例としてジャパンネット銀行の事例を紹介したい。
従来ジャパンネット銀行では、電話サポートを中心としたお客様サポート体制を構築してきた。しかし2017年ごろに発生した入電の増加をきっかけに電話窓口を担う人材不足が顕在化し、LINEのチャットボットおよび有人チャット、Webチャットボット導入に踏み切った。さらにWebを利用しない層からの入電を削減するべく、ビジュアルIVRの活用も行っている。
ビジュアルIVRは各問い合わせチャネルをスマホ画面上のメニューに集約した上で、顧客を各チャネルに誘導していくという仕組みである。
KDDIエボルバのビジュアルIVRにはコールバック予約、混雑状況案内などの機能が備えられており、顧客の多様な問い合わせニーズに柔軟に対応できる。また電話問い合わせ時に流れる音声ガイダンスを使って、顧客をSMS経由でビジュアルIVRに誘導するアプローチも行っている。
これらの取り組みにより、緊急事態宣言中の電話窓口短縮営業中も1万件以上の利用があり、機会損失を防ぐことに成功している。
ビジュアルIVRをはじめとしたデジタルチャネルは、センター運用の縮小や突発的な入電の増加といった非常時にも有効だ。実際多くの導入企業様で「緊急事態宣言中に利用が増加した」との声をいただいている。
さらに、デジタルチャネルには、休日・夜間や混雑時にユーザーの自己解決を促す機能もあるため、現場の負担を減らす効果も期待できる。デジタルチャネルは単体での機能性だけでなく、人的オペレーションをサポートする役割も持ち、CX向上に寄与するものである。
今後も弊社では、コールセンター運営で培ったノウハウを生かし、デジタルと人的オペレーション、双方での提案を通じて、より顧客満足度の高い、そして、より効率的なセンター運営の支援を行っていく所存だ。
株式会社KDDIエボルバ:https://www.k-evolva.com/
三菱UFJ信託銀行のAIを活用したマーケティングの取組について

- 基調講演➁
【講演者】
-
三菱UFJ信託銀行株式会社
業務IT企画部 企画G 調査役岡田 拓郎 氏
- 基調講演➁
【講演者】
-
三菱UFJ信託銀行株式会社
業務IT企画部
(三菱UFJトラストシステム株式会社から出向)高嶋 渉 氏
従来、金融機関のマーケティングといえば、イベントマーケティングなどが中心であったが、ここにきて注目を集めているのがAIを活用したマーケティングである。大量の顧客データをAIに学習させ、顧客の行動を予測するという手法だ。実はAIとマーケティングは相性がよく、うまく活用できれば結果につながりやすい。当社でも現在マーケティング領域において、積極的にAIの活用を推進しているところだ。
AI活用に至るまでには「ゴール設定」「開発」「利用」の3つのステップがある。
まず「ゴール設定」については、顧客のカスタマージャーニーにおけるどの領域でAIを適用するのか、各社の営業戦略にしたがって決定することが重要である。マーケティングやAI活用ではすべてが成功する訳ではないので、小さく始めて、うまくいけば大きくする「スモールスタート」を意識している。
次に、「開発」についてである。AutoMLの登場によってAI開発そのものは数年前に比べると容易になっている。重要なことは、どのデータをAIに学習させるか、そして集めたデータをどう活用するかだ。この2点を間違えてしまうと、効果的なAI活用ができなくなってしまう。顧客本位のAIとは、最適なタイミングで提案を行い、顧客の課題解決へと導くものでなければならない。そのためには、ペルソナの課題やライフプランといった適切なデータを学習させる必要がある。
第3ステップである「利用」、これがもっとも難しい。利用段階においては、現場の壁、リピーターの壁、本番システムの壁という3つの乗り越えるべき壁がある。
そのうちの現場の壁、リピーターの壁は、AIを使う側とAI開発する側の両方がコミュニケーションを取って、歩み寄る必要がある。AIを開発して終わりではなく、利用しやすい業務フロー、AIが出した結果の現場の納得感、それらすべてが揃って初めてAI利用が推進される。
また本番システムの壁は、金融機関にありがちの問題であり、本番システムにいきなりAIを導入するのではなく、スタンドアロンPCで開発、利用してみるなど、先ほど紹介したスモールスタートの考え方が役に立つと考えている。
さいごに人材の育成も重要だ。どんな情報を学習させるのかについてはデータサイエンスの知識が不可欠だが、これを社外のベンダーに任せるとノウハウ蓄積が進まない。こうした望ましくない事態を防ぐためにも、データを適切に扱えるデータサイエンティストは内製化するべきだ。
当社では、2019年10月にAIのCoE組織を立ち上げた。そこにシステム子会社である三菱UFJトラストシステムも参画。三菱UFJトラストシステムには、先端IT 技術を研究、開発するITイノベーション推進部があり、AI専門チームも存在する。データサイエンティストが在籍しているため、ノウハウ蓄積は順調に進んでいる。
現在は、三菱UFJトラストシステムから高嶋含め3名が、親会社である三菱UFJ信託銀行に出向し、AI案件のプロジェクトリーダーを担っている。今後も、AI人材の育成には注力していく。
現在マーケティングにAIを活用している金融機関はそれほど多くはないが、AIを活用するシステム部門の立場から見ると、マーケティングはAIの活用効果が上がりやすい領域である。データが集まれば傾向を掴むのが容易である、実際の効果につながりやすい、といった特徴があるからだ。AI活用にこれから取り組もう、という企業にとっても、マーケティング領域は取り組みやすい分野であると考えている。
顧客中心のコミュニケーション実現
~データを活用し、CX(顧客体験)を向上させるには~

-
【講演者】
-
株式会社プレイド
Business accelerator金田 拓也 氏
プレイドはCXプラットフォームKARTEの提供を通して、金融機関様をはじめとした多くの企業様をCXの面でサポートしてきた。CX、すなわち顧客体験をいかに高めるのか、そして顧客体験をどう事業につなげるのか。これが当社にとってのメインテーマであり、今も日々向き合い、よりよい「顧客体験」を追求するための歩みを進めているところである。
「CX」はふだん目にする機会も多い言葉であるが、一方で漠然とした言葉でもある。
それでも、あえて我々がCXを定義するとしたら、次のようなものになろう。CXとは、商品やサービスの「価格」や「機能性」といった物理的な価値だけではなく、サービスの利用前後を含むあらゆるタッチポイントにおける顧客の「満足感」や「喜び」といった感情や体験の価値も含めた概念である。あくまでも抽象的な概念であって、これが唯一の「正解」といえるものはない。なぜならCXの在り方は機能1つ1つの差分で決まるのではなく、前後の文脈や顧客の満足感を通して決まるものだからだ。本当の意味でのCXを捉えるためには1つ1つの点で捉えるのではなく、背景にあるストーリーを重視する必要がある。
このような性質を持つ以上、CXは決して数字化あるいは定型化できるようなものではないのだ。しかし、ここで1つだけ忘れてはならないことがある。それは、顧客満足度の高いプロダクトは「事業や収益に貢献する」ということだ。CXを追求することは、企業の収益にとってもプラスになる。これはすでに統計学的に明らかにされているところであり、こうした結果を受けて多くの企業の担当者が顧客体験を重視するようになっている。現在すべての商品・サービスは「お客様目線から考えるもの」になりつつある。企業側から自社のプロダクトを押しつけるのではなく、顧客がほしいタイミングでほしいものを提供する――顧客起点でプロダクトの提供が始まる時代がきているのだ。
これを今回のデジタル活用という観点から捉えると、収集した顧客データをどう施策に生かすかという話になる。ここで重要となるのは、データを「人」として見ることだ。データを活用した施策となると、生のデータをどう扱うのかという数字の話になってしまいがちなのだが、それではCXにつながるアイディアは出てこない。データをデータとして見るのではなく、すべての主語を「人」に置き換え、人とのコミュニケーションの延長で向き合う姿勢が必要だ。特にコロナ禍では、データを「人」として捉えて向き合う重要性は増していくと我々は考えている。オンライン上の接点が日常的なものになり、逆にこれまでのようなリアルの店舗には行きにくい状況になっているからだ。
このような状況下で顧客体験を高めるためのコミュニケーションを行うためには、オンライン上でのコミュニケーションを手厚くし、顧客1人1人への理解を深める必要がある。
我々のプロダクトであるKARTEも、まさに上記のような思想のもと、蓄積した顧客データを人として判別・整理し、リアルの現場における良質なコミュニケーションを助けるために作られたツールだ。
顧客の行動をデータとして蓄積できるのは、デジタルならではの強みだ。ただ物事を人として捉えることで、すべてのお客様とのコミュニケーションは点ではなくストーリーになる。そして、そのストーリーに対して企業側がどう向き合い、サービスや商品を提供していくのか。これらの発想が、今後のCXを考える上でいっそう大切になってくるだろう。だからこそ人の感情とデータの効率性という一見相反する二者について、我々は今後も考えを深めていきたい。そしてクライアントそれぞれの事業に対する経営課題や目的に合わせるような形でコミュニケーションを共創することができればと考えている。
株式会社プレイド:https://plaid.co.jp/