- SMBCグループにおけるイノベーション創出に向けた取組について
- 三井住友カードが実現する顧客中心のDigital Communication
- 人とテクノロジーが融合した金融オムニチャネルの姿
- 事例にみるカスタマーデータプラットフォームを活用したデジタルマーケティング
- AI×BI最新データ活用事例
- 少人数からでも始められる「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」への第一歩
SMBCグループにおけるイノベーション創出に向けた取組について

-
基調講演
【講演者】
-
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
ITイノベーション推進部 上席部長代理山﨑 英 氏
日本のフィンテックの発展は遅れていると指摘されることがあるが、一概にそうとは言えない。例えば、送金の即時着金は、フィンテック企業がそれを実現した米国と異なり、日本では既存の金融サービスとして定着している。公的社会保障が手厚い日本では、預金志向が強いため、投資や融資のニーズも米国ほど強くない。これらの違いを踏まえると、単純な他国比較には意味がないと考えている。ただし、キャッシュレス化、UI/UX向上、業務効率化等、日本でも取り組むべき課題は多いと言えるだろう。
フィンテック企業と金融機関の関係性は、競合ではなく、補完し合うパートナーだという見方が、現在グローバルで主流となっている。日本でも、PFMやロボアドバイザー等、金融機関が単独では提供できない、もしくは不得意な分野で、フィンテック企業の成長が目立っている。今後はいかに様々なプレイヤーと協業してエコシステムを構築し、顧客の高い期待に応えていけるかが勝負となるだろう。
新サービスの受け入れは、ITリテラシーの高い層と一般ユーザの間でギャップがあるため、フィンテック企業が市場を切り開き、金融機関が安心感を与えながら広く普及させていくという連携が、日本におけるイノベーションのあるべき方向性だと考えている。
SMBCグループでは、オープンイノベーションを進めるために、まず、社内向けの情報発信や問題提起を積極的に行い、役員も巻き込んだ議論の場を多く持つことで、自発的な参画メンバーを集めた。次に、そこで生まれたアイデアをプロジェクト化し、実績の流布を行うことで、各部署から多くの応用アイデアを集めた。そして、出来るだけ多くのアイデアをプロジェクト化できるよう、予算措置も含め、実行の場を提供するというプロセス経ることで、組織的にイノベーションを支える体制を整えてきた。
オープンイノベーションの場として提供しているhoops link tokyoには、日々様々な業種や規模の企業が集まり、アイデアの議論やイベントが活発に行われている。我々は、米国や東南アジア等のイノベーションの中心地にも拠点を設け、スタートアップや地場銀行との提携にも力を入れている。
既に事業化したプロジェクトをいくつか紹介したい。複数社との協働で設立したPolarifyという企業では、指、顔、声で認証可能な生体認証プラットフォームを提供しており、SMBCグループ以外でも導入が始まった。
決済分野でも、次世代プラットフォームの構築を進めている。日本のキャッシュレス決済を進展させるため、各事業者がいかに簡単に導入できるかを重視しており、事業者とユーザ双方が様々な手段を選択できる仕組みを準備している。
融資分野では、入出金データ等による企業の業況変化予測に人工知能を活用し、取引先支援の高度化に取り組んでいる。業種に依存しない高精度の標準モデルを構築することで、融資業務を高度化していく。人工知能は、AML業務や顧客問合せ対応の現場でも活用し、大幅な省力化を実現している。APIについては、開放するだけでは意味が無いとの考えから、ワークショッププログラムであるSMBC Brewery等を開催しながら、積極的に協業の機会を探っている。
金融イノベーションを加速させるためには、単なる「予測」ではなく、あるべき未来像を「展望」しながら、各社自らが積極的に新しいテクノロジーを利用し、業界にフィードバックしていくことが重要だ。また、テクノロジーの急発展が、我々にとって好ましくない方向に進んでしまうことが無いよう、負の側面にも適確に向き合いながら、取り組んでいくことも大切だと考えている。

三井住友カードが実現する顧客中心のDigital Communication

-
【講演者】
-
三井住友カード株式会社
統合マーケティング部長佐々木 丈也 氏

-
【講演者】
-
株式会社セールスフォース・ドットコム
マーケティングクラウド本部
部長伊奈 憲一郎 氏

-
【講演者】
-
株式会社セールスフォース・ドットコム
ソリューションエンジニア本部
プリンシパルソリューションエンジニア館野 武正 氏
顧客のデジタル移行に伴い、よりパーソナライズされた金融サービスが求められる中、金融機関は必ずしもそれに応えられていないことが多いのが現状だ。テクノロジーの普及で顧客との接点が急増する中、顧客主体のコミュニケーションとサービス設計が、より一層求められている。
セールスフォース・ドットコムは、デジタルマーケティング、店頭、コールセンター等の各業務に合わせた業務支援アプリケーションと、それを一元管理できるサービスを提供することで、多くの金融機関のイノベーションをサポートしてきた。Salesforce Marketing Cloudは、商品認知から成約までの一連のカスタマージャーニーの中で、顧客の行動を分析しながら、最適なアクションやOne to One
コミュニケーションの自動実行を支援するもので、新しい顧客エンゲージメントの実現を支えている。
三井住友カードは、Marketing Cloudの活用により、顧客接点の再構築に成功した1社だ。徹底したデジタル化を経営計画に掲げ、データ分析、戦略、施策実行を全部門横断的に管理する体制を整えて、CXと業務効率化の分野に積極的な投資を行ってきた、同社の取組みを紹介したい。
各部門が売りたい商品の情報をマス配信するという従来のマーケティングは、メール配信拒否の増加等、マイナスの効果を生んでいた。ここに危機感を感じたことを契機に、各部の現場から担当者を集め、カスタマージャーニーに沿ったシナリオやあるべき姿を議論しながら、ボトムアップの改革を開始した。発信情報は顧客が関心を持つものに限定し、最適なタイミングと手段での配信を徹底することで、期待を上回る顧客体験の提供を目指している。
これを実現する仕組みとして、メール、SMS、モバイルアプリ等のチャネルを一元管理し、One to Oneコミュニケーションとマーケティングオートメーション(MA)を可能にするMarketing Cloudを導入した。
配信コンテンツはデザインにこだわり、細かいレベルで効果検証ができる体制を整えて、多くのシナリオをMarketing Cloud 上で実行している。例えば、リボ払い設定対象カードであることが入会時に正しく認識されず、後にトラブルへと発展するという課題を解決するため、カード到着のタイミングに合わせ、分かりやすいサービス説明のコンテンツを配信した。これにより、問合せと解約は大幅に減少し、これに起因するクレームもほぼ撲滅することができた。また、カード不着時に不在票が認知されず、再送しても受取られないケースの改善策として、カード不着時の顧客あて通知を行った結果、10%の受取率向上に成功している。
新規入会直後のプロモーションは、一斉にあらゆる通知を行うのではなく、例えば入会直後はカードの利用方法を分かりやすく伝えるコンテンツに絞り、初回利用後に、日常利用の促進やEC促進等、その顧客の利用実績に合わせたプロモーションを展開する等、パターンを複数分岐させながら展開した。その結果、カードの利用率や利用単価の向上等、着実に効果が表れている。
三井住友カードは、さらなる発展に向けたチャレンジも行っている。顧客の潜在ニーズ発掘と、より高精度のターゲット選定の実現を狙いとして、今後はデータ分析にAIを取り込む方針だ。RPA活用も単なる合理化に留めず、顧客からの問合せ対応のスピード向上に応用している。コンテンツ作成にもこだわりを持っており、複数のデザインを用意して、その時の顧客に響くものをリアルタイムで選別しながら展開できる仕組みを整えている。「顧客にとって心地良い瞬間を、いかに多く届けられるか」というテーマを改革の軸としながら、積極的な改革を進めている。

人とテクノロジーが融合した金融オムニチャネルの姿

-
【講演者】
-
富士通株式会社
デジタルフロント事業本部 デジタルビジネス事業部
カスタマエンゲージメントソリューション室 シニアディレクター倉知 陽一 氏

-
【講演者】
-
ジェネシス・ジャパン株式会社
ソリューションマーケティング
マネージャー正木 寛人 氏
顧客接点におけるCX向上やデジタル化はグローバルで大きなテーマである。すでに海外ではオムニチャネル化によって利便性を高めることが顧客のNPSスコアや購入商品に影響を与えるケースも見受けられる。顧客のモバイルシフトは他国と比べて遅れているが、今後、顧客のデジタルシフトは急速に進む事も予想され、顧客と取引金融機関の関係構築を変える可能性を持つ顧客接点のデジタル・トランスフォメーションは喫緊に取り組むべき課題になりつつある。
現在多くの金融機関では、店舗やウェブ等の種類毎に顧客を管理するマルチチャネルから一歩進み、複数チャネルを利用する同一顧客の情報を一元的に把握できる、クロスチャネルに到達。しかし、顧客の高いエンゲージメントを形成するには、得られた情報を効果的なアクションに活かし、一貫性のある顧客体験を提供し得るオムニチャネルへと発展させる必要がある。
ジェネシスでは、コールセンター基盤をベースに、メールやチャット、SNS等のデジタル・チャネルまで包括したオムニチャネルの顧客接点のマネジメントを実現できるCX基盤を提供。最近リリースしたLINEのカスタマーコネクトとの連携機能では、既存顧客の問合せ対応に加え、新規顧客獲得の場面でも大きな効果を上げた導入例もある。さらにCRMシステム等との連携機能、分析機能、モバイル対応やBPMシステム連携、IoTへの対応等、高度な顧客対応を実現するための機能をビジネス課題に応じて柔軟にサポートできる。
ここ数年、顧客接点についてはAI(人工知能)の活用が話題である。ジェネシスにおいても“ブレンデッドAI”というコンセプトの下、機械学習をベースにお客様と対応リソースのマッチングを最適化するPredictive Routingやウェブ上のお客様の行動と購買予測から最適なオファーリングを行うAltocloudといったソリューションを具現化している。さらに顧客対応用のチャットボットやAIと人による対応を融合させた自動化を推進しており、この分野では富士通とパートナーシップを組んでいる。
コンタクトセンターでの応答をAIで自動化しようとする場合、膨大な教師データを要するが、既存の問合せ履歴は会話内容が要約されていることが多く、教師データとして活用できないケースが多い。
富士通が提供する対話・機械学習ハイブリッド型のAIは、少量の教師データで、平均80%という高い回答精度を実現できるもので、問合せ対応の自動化に非常に適している。AIが利用者の言葉のゆらぎを吸収し、企業が用意する公式FAQに対応する言葉に置き換えて検索するこの仕組みは、ディープラーニング型に比べて短い期間で利用を開始できることもあり、あらゆる業界の企業に導入することができる。
これを導入した某大手金融機関では、24時間365日体制でのウェブ完結リアルタイム回答を、既に実現。家事代行のマッチングサイトでは、メールの問合せ件数を増やすことなく、新規利用顧客の急増に対応しており、チャットで収集した声を分析して新サービスに活かす等、単なる合理化に留まらない活用へと発展させている。
富士通が提供するCHORDSHIPは、チャットボット等のICT活用による顧客接点高度化を、導入コンサルティングから、AIとヒトの最適なハイブリッド運用まで、トータルでサポートするソリューションだ。問合せ対応に適したチャットボットを装備したDigital AgentをSaaSとして提供し、各種SNSを含めたあらゆるチャネルからの利用を可能としている。これを業務システムと連携すれば、プログラム開発を要さずに、手続きの自動化を実現することも可能だ。
消費者の行動や感性に合った最適なデジタルシフトが実現できるよう、ジェネシスと富士通は一体となり、あらゆる企業をトータルでサポートしていきたい。

事例にみるカスタマーデータプラットフォームを活用したデジタルマーケティング

-
【講演者】
-
トレジャーデータ株式会社
マーケティングディレクター堀内 健后 氏
企業を取り巻く環境変化のスピードは、最近特に加速しているが、その中で、特にグローバルで急成長している企業のビジネスには、「データ活用により、パーソナライズした顧客体験を提供している」という共通点が見られる。パーソナライズやOne to Oneコミュニケーションが注目されるようになるにつれ、それを支えるデータの重要性も高まっていると言えるだろう。
マーケティングのデジタル化は非常に重要だ。これにより、デジタル上で起こる全ての活動の計測と検証可能性が上がり、実験や改善のスピードも向上する。しかし、デジタルマーケティングは、1つのコンテンツに対して、顧客が選択するデバイスと媒体が多岐にわたる中で、さらに届ける情報をパーソナライズしようとする、非常に複雑なものだ。
また、最近はカスタマージャーニーも複雑化している。既存顧客による口コミが次の顧客を呼んでいた従来のモデルと異なり、現在は、潜在顧客に商品等が認知された瞬間から、SNSで情報がシェアされるため、購買前の段階から顧客行動をよく把握する必要がある。これらは容易に取り組めるものではない。顧客を理解し、適切にコミュニケーションをとり、効果検証をするというサイクルを効果的に推進するには、全ての根拠となるデータをいかに多く収集して、分析管理できるかがポイントとなる。
当社は、カスタマーデータプラットフォーム(CDP)をクラウド上で提供する、シリコンバレー発の企業で、現在日本では、ネット系や消費財系の大手企業を中心として、約300社に利用されている。
CDPは、広告やアプリログ等のあらゆるデータソースから顧客データを収集して蓄積し、統計データや天気情報等の外部DMPと連携して分析し、各種マーケティングツールに施策を連携できる仕組みを構築している。社内各部でサイロ化された顧客接点を横断的に管理することで、よりパーソナライズされたコミュニケーションを実現する基礎として利用されることを目的に開発した。
CDPの活用範囲は幅広い。可能性の高い見込み客を導き出すための、AI活用によるリードスコアリングの自動化は、新規顧客獲得のみならず、解約リスクの検証も行える。加えて、複数デバイスを利用している同一顧客の推定や世帯特定も可能であり、これは保険や相続関連の提案にも利用可能だ。
他にも、位置情報を利用した地域特定キャンペーンの立案や、自動車運転情報から保険料を算出するテレマティクス保険等、あらゆる分野で活用できる。さらに、ビジネスイノベーションを起こす仕組みとして、業界を跨いで顧客単位の行動データを企業間で連携できるエコシステムもできつつある。
フィンテックは世界各地で発展の傾向に特徴があるが、特に最近の欧州は、大企業とスタートアップの連携の場面で、米国と異なる動向を見せている。例えば、クライアント側の大手企業がスポンサーとなり、国をあげて行われるフランスのViva Techでは、あらゆる業界の大企業による出展が目立つ。そこで自らの戦略や課題等を積極的にオープンにすることで、集まるベンチャー企業を巻き込もうというスタンスだ。
大手企業によるスタートアップの支援の仕方にも特徴がある。単なる出資だけには留まらず、例えば自社研究施設内にラボを構え、技術、人、設備等、自社の膨大なアセットを提供しながら、自社の課題をオープンイノベーションで解決しようとする動きがある。これらは、IT系スタートアップ側が主導して、連携する大企業を探すことが多い日本に比べてスピード感があり、我々としてもこれを参考にしながら、多くの企業が連携してイノベーションが生まれる環境作りに取り組みたい。
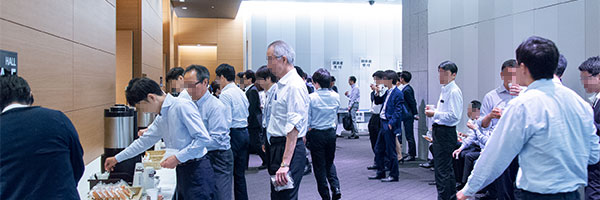
AI×BI最新データ活用事例

-
【講演者】
-
Tableau Japan 株式会社
セールスコンサルタント津久井 英樹 氏
Tableauは、企業に蓄積されたデータを分析・可視化し、意思決定をサポートする「ビジネスインテリジェンス(BI)」のプラットフォームだ。創業以来「ヒトがデータを見て理解できるように支援する」ことを掲げ製品開発を行い、ガートナー社が発表するマジッククアドラントのBI/分析分野で、6年連続「リーダー」の評価を受けている。
Tableauは、楽しみながらデータと会話をできるツールとして、世界中のユーザーから圧倒的な支持を得ている。データがあるところであればどんな領域でも活用の可能性があり、特にデータの「可視化(ビジュアライゼーション)・分析」と、その結果の「共有」のプロセスにおいて強みを持っている。
Tableauの具体的な機能について紹介したい。まず、データの読み込みにおいては、ファイルベースのデータはもちろん、システムやSaaS内に保存されているデータにも対応しており、データを一度も吐き出すことなく、Tableauひとつで読み込みから分析の流れに進むことができる。基本操作もいたってシンプルで、読み込んだデータ項目を分析領域にドラッグするだけで答えが返ってくる。
例えば「売上」という項目をドラッグすれば、売上合計が棒グラフで表示されるといった具合だ。グラフの並べ替え、タテ/ヨコ表示の切り替えなどもアイコンをクリックするだけで簡単に実行できる。
表示された結果の内容が直観的に理解できるよう、グラフの色や大きさが効果的に使われている点もTableauの強みだ。スタンフォード大学の研究プロジェクトをベースに、いかに人間にデータの内容を素早く認知させるかに特化している。データの内容が画面上で直観的に理解できれば、分析を進める際の仮説検証作業を容易に進めることができる。手順が煩雑なExcelでの分析などに比べ、より先の分析まで進みやすく、新しい気づきを得る可能性が広がる。このように、可視化しながらデータを分析していくプロセスのことをビジュアル分析と呼んでいる。
分析結果を組織内で活用するには、結果の共有が必要だ。Tableauは、分析結果に公開設定を付すことで、ブラウザ経由で閲覧が可能になる。閲覧時の最新データで結果を確認し、ブラウザ上でデータを操作することも可能だ。ブラウザ以外に、メールでのレポーティングにも対応している。
Tableauプラットフォームは、さらに機能の深化に努めている。ダッシュボード スターターという新機能では、Salesforce、Marketo、Oracle Eloquaなどのサービス利用者がTableauを契約すると、あらかじめ用意されたテンプレートを選択するだけですぐにベストプラクティスに基づいたいくつかのダッシュボードを表示できる機能を備えた。データ分析にあまり親しみがない人も含め、すべての方にデータに触れていただき、多くの気づきを得て企業の競争力を上げていただきたい。
現在構想中ではあるが買収した企業の技術をもとに、データに対し自然言語で質問をするとそれに合わせた結果が可視化されて返ってくるというサービスを開発している。キーボードや音声認識で自然の会話を通して分析結果を得ることが可能になる。
また、APIを使った他サービスとの連携も進めており、例えばAutomated Insights社のWordsmithとの連携では、分析結果をグラフだけでなく自然言語でも出力されるようにしている。AIが作成した解説文に対し、人がより深掘りすべき個所を指示することで、AIが再び分析結果を自然言語で示すという連続的で拡張的な分析も可能だ。
データ活用を活発化していくには、いかに楽しく親しみを持ってデータに接していただけるかが重要だ。Tableauは今後も、どなたでもわかりやすくデータに触れていただけるように支援していきたい。Tableauの製品は無料トライアルも可能だ。ぜひお手持ちのデータで、データ活用の楽しみを感じていただきたい。

少人数からでも始められる「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」への第一歩

-
特別講演
【講演者】
-
住信SBIネット銀行株式会社
ビッグデータ部長 審査第1部部長
AI審査サービス創出プロジェクトチーム長山縣 崇之 氏
本日はデジタル・トランスフォーメーション(DX)をテーマに、その目的や金融機関における価値を考察しつつ、当社での実際の取り組みについて紹介したい。
当社ではこれまで、様々な業務領域のデジタル化に取り組んできた経験を通じ、DXとは「期待を”超える“顧客体験を通じた、持続的な収益向上を生み出すための取り組み」であることと認識している。DXの一連の取り組みによって顧客の支持を得ることができると、商品の利用増加などにより本業自体の伸びにつなげていくことができる。
期待を超える顧客体験の創出のために、具体的に足元で取り組むべきDXは何であろうか。当社では、金融機関の現場におけるDXの適用場面をいくつかの要素に分類して考えているが、特にビッグデータおよびそれを動かしていくAI/MLの2つが、金融機関が攻略すべきDXの本丸であると考えている。これらは今後継続的に量(データ)の増加と質(技術)の進歩が見込まれるものであり、磨きをかけていく価値があるといえる。
ここからは、実際の当社の取組事例を通じ、具体的な体制や取組方針、実施方法について紹介していきたい。
我々のプロジェクトは、2年ほど前、専属スタッフ3名、データサイエンティスト不在の状況でスタートした。DXを進めるには、データ分析・ビジネス設計・インフラ整備の3つの資質を具備する人材を用意する必要があるが、実際には難しく、各々を得意分野とする人材で三位一体にて補完し合うのが現実的である。
また増員計画を立てる上では、企業ごとの固有の課題に合わせ、3つの機能のどこを優先的に増員すべきかを予め決めておくことが重要だ。当社では、分析・設計・整備をさらに細分化し、必要なスキルを予め決めたうえで、数か月サイクルで組織の重心位置を変えていけるように運営した。
続いて方針を決める段階では、一か月程度で決定を行った。時間をかけて細かい方針を決める必要はなく、まずはテーマを判断するための基準を決めれば十分だ。実際の試行段階では、複数のプロジェクトを並行させながらアジャイルに推進した。また、成否判断をロジカルに行うために、予めKPIを決めておくことが非常に重要だ。技術を業務に適用する際は、「実現できること」と「実現したいこと」を統合するため、技術リストと業務分掌リストの突合せを行った。
先端技術との向き合い方についても述べておきたい。どの企業も必ず取り組まなければならない課題である一方、個別の技術に一度に対応しようとすると必ずリソース不足になる。当社では、顧客体験の向上に寄与するかを軸にコア領域とノンコア領域に分けて考え、マーケティングや審査など、リテール銀行としてのコア領域では1stムーバーを目指し、それ以外のノンコア領域は1stフォロワーとなることを選んだ。
以上のようなDXの取り組みを通し、当社ではいくつかの学びを得た。まずビッグデータについて、画像・音声・感情などをデータで表現することが可能になったことにより、その価値は更に高まっていることが再認識できた。あらゆる技術が進化しても依然として価値の源泉はビッグデータにある。同時に、ビッグデータを活用していくには、データのクレンジング・加工といった前処理が重要であり、この前処理の巧拙がビッグデータ活用の成否を左右することも学んだ。
また、組織の面では、従来組織の延長といったプロジェクトチームではなく独立組織としたことが効果的であった。これにより、予定調和的なプロジェクト進行を排除し、顧客視点を忘れることなく変革と創造を貫くことができた。DXには決して近道は存在しない。顧客や現場の声に耳を傾けながら地道に対応していくことが必要だ。











